フレックスタイム制とは?
導入するために
知っておきたいこと
働き方改革の一環として、フレックスタイム制を導入するという話を耳にすることがあります。しかし、どのような業態であっても、導入することで働き方改革に結びつくものなのでしょうか。業態によっては、フレックスタイム制は合っていないかもしれません。そこで、この記事では、フレックスタイム制のメリット・デメリットや導入する際の注意点などについて解説していきます。
フレックスタイム制とは
どのような制度?

はじめに、基本的な知識として、フレックスタイム制とはどのような制度なのか説明していきます。「フレックスタイム」とは、あらかじめ決められた総労働時間の範囲内で、始業時間や終業時間を労働者自身が自由に決められる制度のことです。例えば、1カ月あたりの総労働時間が160時間と決められているとしましょう。この総労働時間の範囲内であれば、8時間労働になる日があっても6時間労働になる日があってもよいということです。また、ときには10時間になる日があるかもしれません。
フレックスタイム制は、1987年の労働基準法改正で導入され、労働基準法第32条の3に定められています。フレックスタイム制の大きな特徴は、勤務時間が何時から何時までと固定されていないことです。一般的な働き方とは違い、出社時間や退社時間が会社によって決められているわけではありません。1日の労働時間も、労働者自身が決めることができます。最終的に総労働時間に達していれば、労働者が自分の都合に合わせて調整できる働き方です。
フレックスタイム制の仕組みは?
フレックスタイム制は、労働者自身が自由に調整できる働き方ですが、一定のルールはあります。
では、フレックスタイム制の仕組みについて解説していきます。
仕組み1
コアタイムとは?
説明したように、フレックスタイム制は始業時間と終業時間が固定されていない制度です。何時に仕事を始めて何時まで働くかは、労働者自身で決めることができます。しかし、だからといって24時間いつでも自由に出退勤できるかというと、そうではありません。1日の中で必ず出勤して仕事をしていなければならない時間帯が設けられています。それが「コアタイム」です。
コアタイムは、労働者間の情報共有やコミュニケーションをスムーズに行うことを目的としています。出社時間や退社時間はそれぞれに違っても、全員が必ず揃う時間があればミーティングの予定を入れやすくなるでしょう。取引先から商談が入ったとき、予定を入れやすいのもメリットです。しかし、コアタイムは、必ず設けなくてもよいことになっています。毎日ではなく、コアタイムを設ける日と設けない日があってもかまいません。
また、日によってコアタイムの時間帯が違ってもよいとされています。そもそも、コアタイムと1日の労働時間がほぼ同じになる場合は、フレックスタイム制とはいえませんん。あらかじめ会社側で決めてしまうと、労働者が出退勤時間を裁量で自由に決めることができないためです。
種類2
フレキシブルタイムとは?
フレキシブルタイムとは、労働者の裁量で自由に出退勤時間を決めてよい時間帯のことです。フレキシブルタイムは、コアタイムの前後に設けられるもので、コアタイムの前もしくは後ろのいずれか一方だけに設けることはできません。コアタイムが始業時間あるいは終業時間になってしまうと、労働者自身で出退勤時間を決められなくなります。
フレキシブルタイムの時間帯は、中抜けすることも可能です。ただし、フレキシブルタイムの開始時間と終了時間は、事前に労使協定で定めなければならないことになっています。労使協定を結ぶ際、フレキシブルタイムの長さは自由に定めることができます。自由に長さを決められるといっても、極端に短い場合はフレックスタイム制とはいえません。例えば、フレキシブルタイムが30分だったとすると、労働者の裁量で出退勤時間を自由に決める余地がなくなるためです。フレキシブルタイムが極端に短いと、フレックスタイム制と認めてもらえないこともあるので注意しましょう。
種類3
スーパーフレックス制とは?
スーパーフレックス制とは、簡単にいえばコアタイムを排除したフレックス制度のことです。コアタイムが設けられていないため、フルリモート勤務なども可能になり、働く場所についても労働者自身が自由に決めることができます。一定期間の総労働時間や総労働日数さえ満たしていれば、いつ出勤して何時間働くかは、労働者が自由に決められる制度です。スーパーフレックス制を導入すれば、労働者の事情に合わせた多様な働き方が可能になります。
スーパーフレックス制を導入する場合、労働者の裁量にゆだねられるのは出退勤時間だけではありません。実質的には、出勤日も労働者にゆだねられます。そのため、企業は所定休日を事前に決めておく必要性が出てきます。スーパーフレックス制は裁量労働制とは異なることから、労働者が実際に働いた時間をカウントしなければならないのも注意点です。そういった問題から、勤怠管理が難しいというデメリットもあります。例えば、営業職のように外回りが中心になるような業務だと、勤怠管理は難しいかもしれません。スーパーフレックス制は、自社内で完結できる業務に向いている制度といえるでしょう。
フレックスタイム制が
向いている職種と向かない職種
フレックスタイム制は、どのような職種でも対応可能なわけではなく、導入にいたっては見極めが肝心です。
向いている職種もあれば向かない職種もあります。

フレックスタイム制が向いている職種
フレックスタイム制の導入が多い職種をあげていくと、事務職や企画職、エンジニア、プログラマー、デザイナーなどです。導入しやすい業種の特徴で見ていくと、外部との接触機会が少ない業種や他人への依存度が低い業種などになります。仕事が細分化されている業種も、フレックスタイム制に向いています。
これらの業種に共通しているのは、自分のペースで業務を進められることです。出退勤時間を自分だけで決めやすいことから、導入しやすい傾向があります。

フレックスタイム制が向いていない職種
フレックスタイム制の導入が難しいのは工場のラインや営業職、接客業、サービス業などです。これらの業種は、自分のペースだけで働く時間帯を決めることはできません。営業職や接客業などは、顧客や取引先と対面でのやり取りが不可欠です。工場のラインのように多くの従業員や企業との連携が不可欠な業務は、フレックスタイム制を導入しにくいといっていいでしょう。
フレックスタイム制は、必ずしもすべての従業員に適用する必要はありません。
導入するからといって社内全体にフレックスタイム制を設けることはなく、特定の部署や個人にのみ適用することもできます。
例えば、内勤業務だけをフレックスタイム制にしたり、育児中の社員に導入したりという使い分けも可能です。
フレックスタイム制を導入する
メリットとデメリット
フレックスタイム制は、よい面ばかりではありません。
そこで、フレックスタイム制を導入するメリットとデメリットについて解説していきます。
メリット
フレックスタイム制を導入すると、従業員のワーク・ライフ・バランスを取りやすい点が大きなメリットです。フレックスタイム制は、働く時間を自由にかつ効率的に配分できます。従業員自身が自分のライフスタイルとのバランスを取りながら、もっとも適したタイミングで働くことができます。例えば、介護や育児をしながらでも無理のない働き方が可能です。
仕事量や内容に応じてメリハリを持たせた働き方ができるのも、メリットといえます。仕事に集中できるタイミングは、誰もが同じというわけにはいきません。特に、クリエイティブな仕事の場合、決められた就業時間内にアイデアがまとまらないこともあるでしょう。集中しやすい時間帯に仕事に取り組むことで、生産性の向上が期待できます。そうなれば、無駄な残業や休日出勤を減らすことにもつながります。その結果、従業員の疲労やストレスが軽減されるかもしれません。
また、企業にとっては、採用の際にアピールポイントとしても有効です。働き方に柔軟性を持たせてある企業という印象を定着させることができれば、働きやすい職場を求める優秀な人材を確保しやすくなるでしょう。従業員が定着しやすいことも、フレックスタイム制のメリットです。
デメリット
フレックスタイム制を導入すると、従業員の勤務時間がずれることから同期型コミュニケーションが難しくなります。同期型コミュニケーションとは、例えばミーティングや電話など、その場での対応が必要になるコミュニケーションのことです。対して、メールやチャットなど即時の回答を必要としないものを非同期型コミュニケーションといいます。
同期型コミュニケーションが取りにくいという問題を解決するには、導入後の情報共有の方法や人間関係構築についてのルールを考えておくといいでしょう。同期型コミュニケーションの問題を考えると、取引先や顧客とのやり取りをリアルタイムで行う部署には向いていません。担当者不在のタイミングが多ければ、取引先の信頼を失ったり顧客満足度を低下させたりといったリスクをともないます。そのため、導入できる職種が限られるのがフレックスタイム制のデメリットです。
従業員によって出社時間と退社時間が異なると、総労働時間の計算をはじめ勤怠管理が複雑になります。この点については、フレックスタイム制に対応した管理システムを導入するなどし、効率的な勤怠管理を目指す必要性が出てきます。フレックスタイム制度に対応するための、勤怠規定の調整も行ったほうがいいでしょう。そもそも、自己管理が苦手な従業員には不向きというのもフレックスタイム制のデメリットです。普段から遅刻が目立つ従業員の場合、時間管理がルーズになる可能性があります。その結果、かえって生産性が低下したり無駄な残業が増えたりするというリスクが発生します。
フレックスタイム制における
時間外労働とは?

フレックスタイム制において、総労働時間を定めた期間のことを「清算期間」と呼びます。清算期間は、法改正によって最長で3カ月まで設定できるようになっています。そして、清算期間内で働かなければならないと決められている時間が「総労働時間」です。フレックスタイム制の場合、清算期間における労働時間の中で総労働時間を超えた部分が時間外労働となり、残業代が発生します。
単に1日の労働時間が長いというだけでは、時間外労働とはみなされません。労働時間が長い日と短い日で調整されており、週や月の所定労働時間内に収まっていれば時間外労働にはならないのがフレックスタイム制の特徴です。ただし、清算期間が1カ月を超えるときは、週の平均労働時間が40時間を超えてはいけないことになっています。さらに、1カ月ごとの労働時間は、週平均で50時間を超えてはいけないことも決められています。
つまり、フレックスタイム制において残業代が発生するケースは、清算期間内の総労働時間が法定労働時間を超えているか1カ月の週平均労働時間が50時間を超えているときです。もちろん、フレックスタイム制でも時間外労働の上限規定が適用されます。残業代を計算するときは、法定残業と法定外残業に分けて計算する必要が出てきます。
フレックスタイム制導入を
検討する際の注意事項
続いて、フレックスタイム制の導入を検討する際の注意事項について解説していきます。
違反とみなされれば罰則を受けることもあるので、事前にしっかり確認しておく必要があります。
3つの注意事項
 労使協定の締結が必須
労使協定の締結が必須
フレックスタイム制の導入には、フレックスタイム制に関する労使協定の締結が必須条件です。このことについては、労働基準法に明記されています。たとえ労使間で合意があったとしても、労使協定を締結していなければフレックスタイム制を導入してはいけません。なお、フレックスタイム制に関して労使協定で定めなければならない事項は次の6項目になります。
1つ目は、フレックスタイム制が適用される従業員の範囲を明確にしておくことです。
2つ目は、清算期間をいつからいつまでにするか決定しておくことです。また、最長でも期間は3カ月以内です。
3つ目は、清算期間の具体的な起算日を定めることです。
4つ目は、清算期間内の総労働時間を決定しておくことです。何時間にするのか明確に決めておかなければなりません。
5つ目は、年次有給休暇の取得についてです。年次有給休暇の取得に対して、何時間として扱うかを決めておきます。その前に、あらかじめ1日当たりの標準労働時間を決めておくといいでしょう。
6つ目は、コアタイムとフレキシブルタイムを設定することです。先述した通り、フレキシブルタイムはコアタイムの前後に設定しなければなりません。さらに、極端に短い時間で設定してはいけないことになっています。
 フレックスタイム制適用を従業員に周知
フレックスタイム制適用を従業員に周知
フレックスタイム制の適用については、全従業員に周知する必要があります。フレックスタイム制の導入が決定し、準備が整った時点で就業規則などで明らかにしておくといいでしょう。このとき「始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる」旨を明記する必要があります。ただ、規定内容まで従業員に完全に認識させることまでは求められていません。従業員が認識したいときにできる状態にしておけばよいということです。
実際には従業員が中身を確認していないとしても、いつでも確認できる状態にあるということが重要になってきます。しかし、そもそも就業規則の存在を従業員が知らない場合や閲覧する方法がわからないという場合は、周知不足とみなされるので注意が必要です。
 清算期間を1カ月超に設定したら労使協定の届け出も必須
清算期間を1カ月超に設定したら労使協定の届け出も必須
フレックスタイム制の清算期間については、かつては1カ月以内に限られていました。しかし、働き方改革を推進するための法改正によって、3カ月まで延長されています。清算期間が1カ月以内の場合と1カ月を超える場合では異なる点があるので、理解しておくようにするといいでしょう。
清算期間を1カ月以内とするときは「労使協定で所定事項を定めること」「就業規則等に規定して従業員に周知すること」の2点は、必須です。1カ月を超える清算期間を設定したときは、先ほどの2点に加えて「労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出ること」も必須になります。もしも、これらに違反した場合は、30万円以下の罰金が科せられるので注意しましょう。ただし、ちょうど1カ月にする場合は、1カ月以内となるので届け出る必要はありません。
フレックスタイム制の
労務管理方法は?

フレックスタイム制は、労働者が労働時間を決めることができますが、だからといって従業員だけに管理を任せることはできません。フレックスタイム制の導入にあたっては、企業は毎日の出退勤時間と労働時間の記録を客観的な方法で管理することが求められます。具体的な方法としては、タイムレコーダーや勤怠管理ソフトなどを活用して管理を行うといいでしょう。労働者側も、月ごとの勤務記録を会社に提出する必要がありますから、自身でも勤務時間を管理しなければなりません。
フレックスタイム制で求められるのは、各自の出退勤予定時刻などの見える化を図り、共有することです。フレックスタイム制は、すべての従業員に適用しなくてもよい制度なので、その分多様な勤務形態を一元管理できるシステムが必要になります。さまざまな出退勤データをまとめて管理することで、複雑な労働時間の集計から残業代の計算に至るまで効率的にこなすことができます。計算ミスも減らせますし、タイムカードや給与計算、シフト管理といったことが一元化できるシステムを活用すると便利です。
フレックスタイム制には
適正な勤怠管理が不可欠
フレックスタイム制は、労働者が自分で自分のタイムマネジメントをする働き方です。だからこそ、適正な勤怠管理を行うことは欠かすことができません。フレックスタイム制を導入する際はもちろんですが、導入しない場合でも適切な勤怠管理をすることは会社にとって重要といえます。効率的で便利な勤怠管理システムの導入については、自社に合うものを選ぶことが大切です。
※スマレジ・タイムカードは
フレックスタイムに対応しておりません。



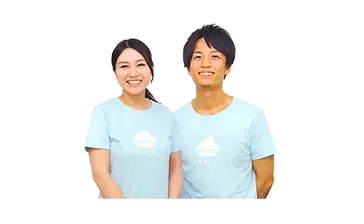



 クラウドPOSシステム
クラウドPOSシステム クラウド勤怠管理
クラウド勤怠管理 オーダーエントリーシステム
オーダーエントリーシステム ECソリューション
ECソリューション 周辺機器の販売
周辺機器の販売 オウンドメディア
オウンドメディア